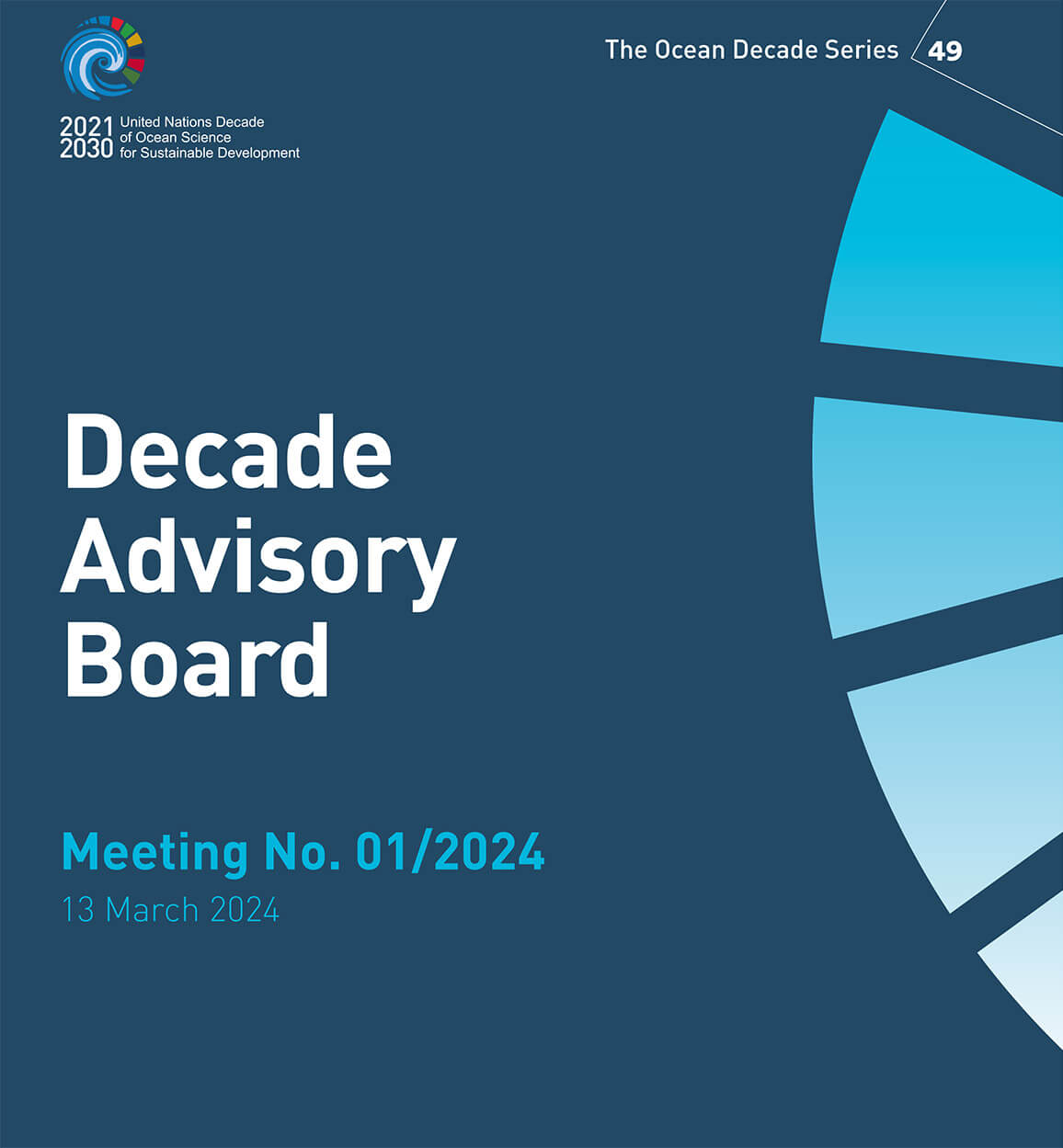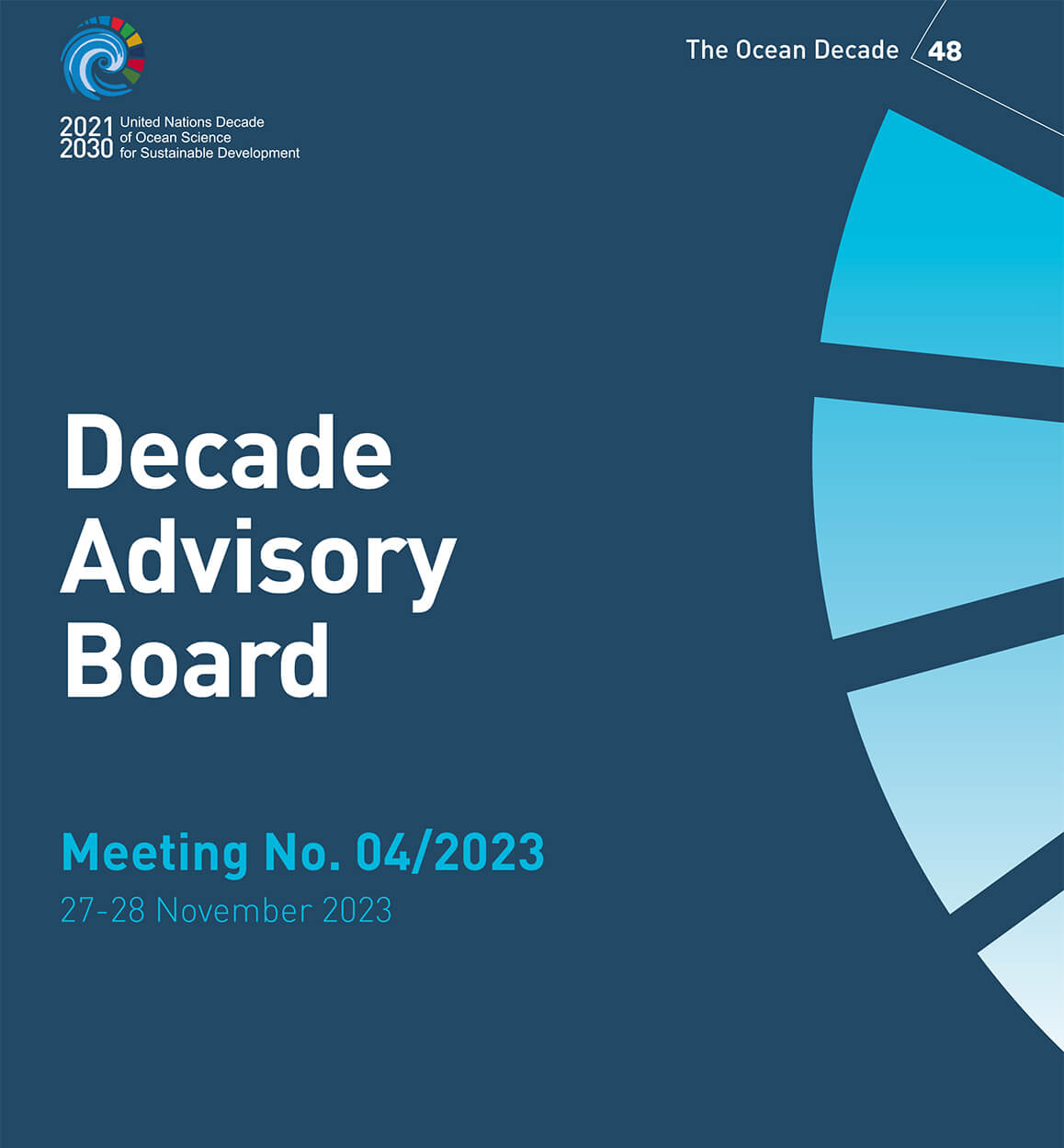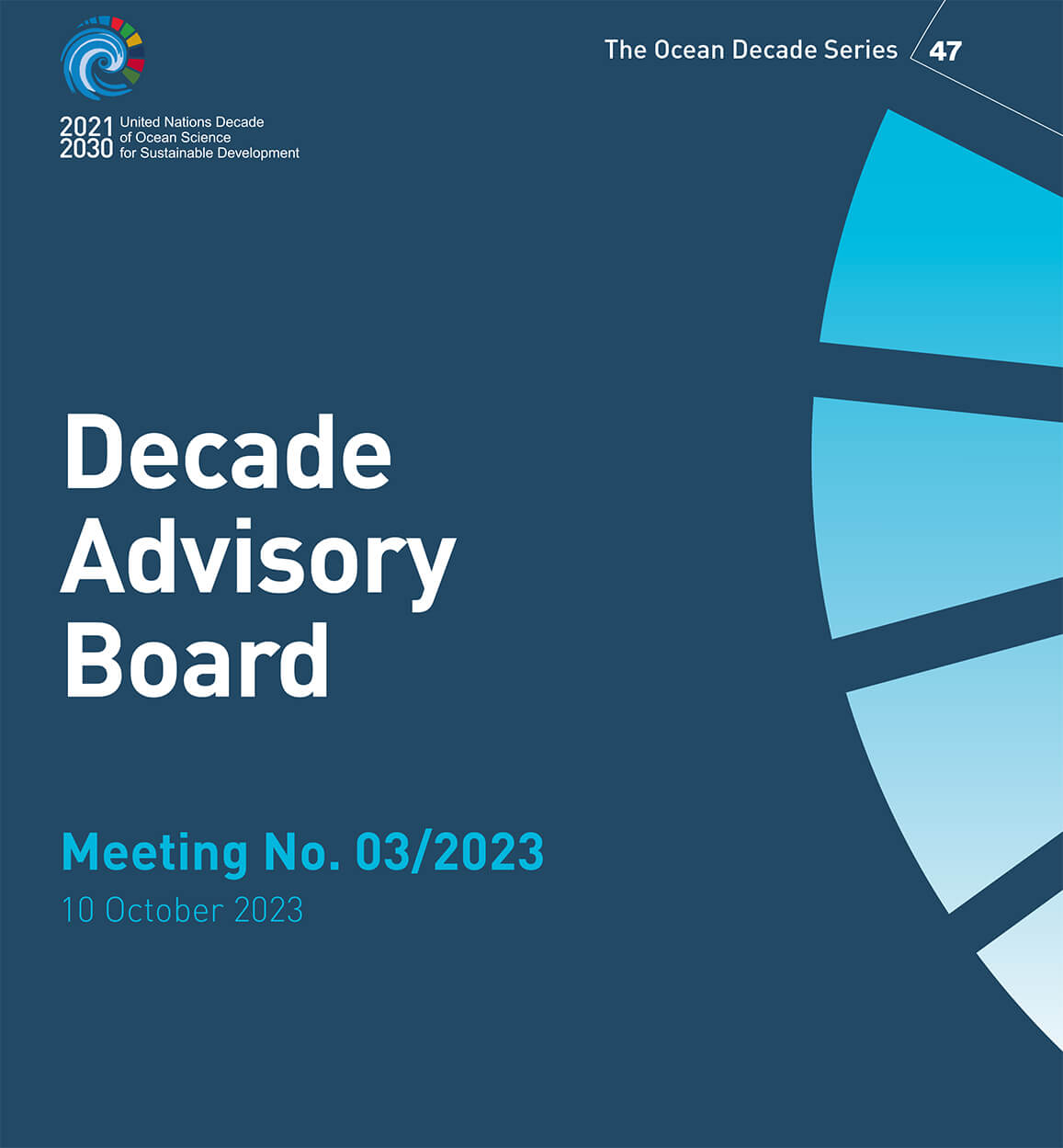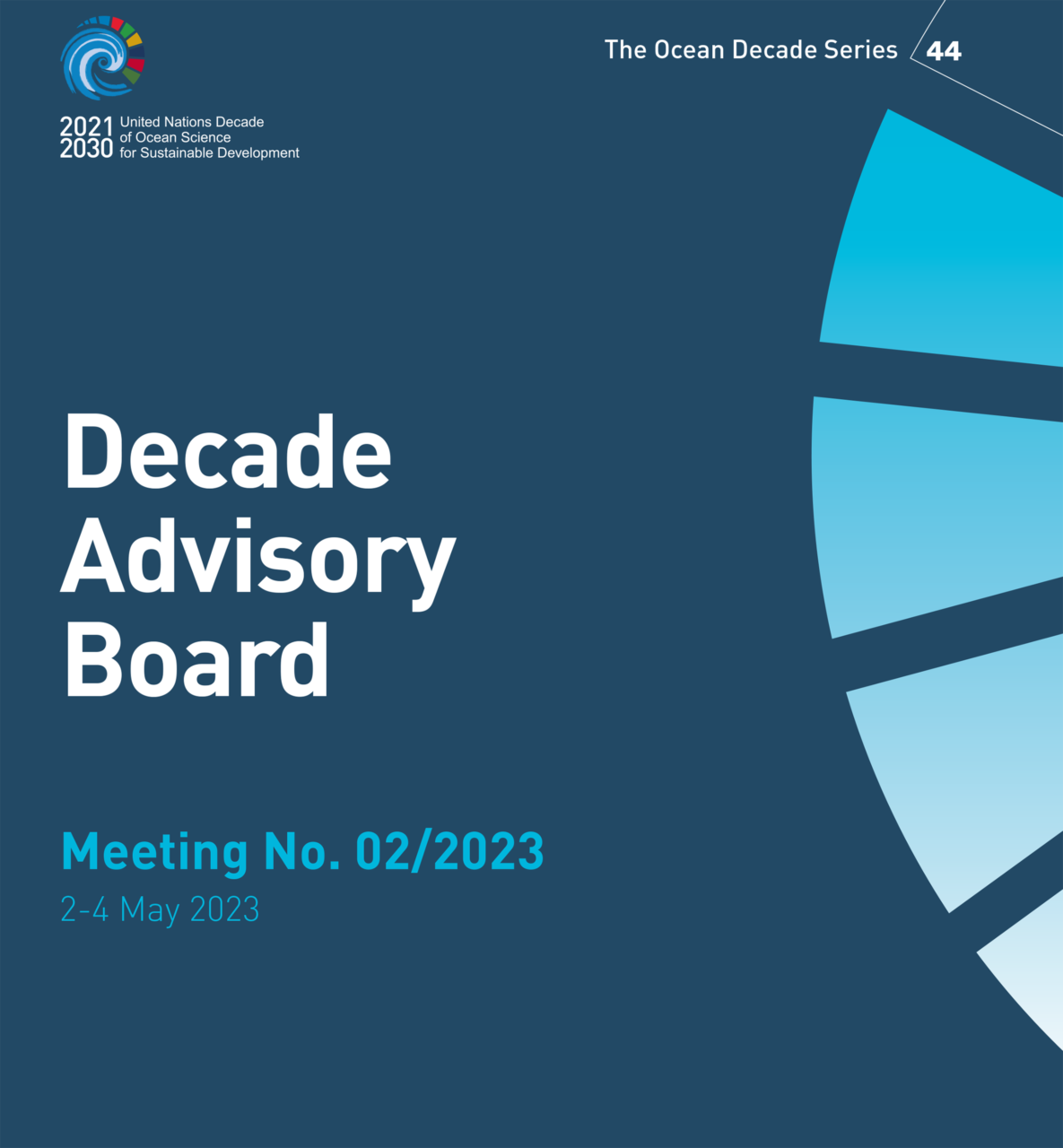10年アドバイザリーボード
10年諮問委員会は、「海の10年」の調整を担当する国連機関であるユネスコの政府間海洋学委員会(IOC)の諮問機関であり、「10年」の実施に関する戦略的なアドバイスを行います。メンバーは2年間の任期で選出され、それぞれの立場で活動します。
10年諮問委員会は、プログラムおよび「10年協力センター」の承認に関する提言を行い、「海洋の10年」行動の連結パフォーマンスについてコメントする。理事会メンバーは、「海洋の10年」の活動に必要な資源の評価にも貢献し、潜在的な資源提供者を含め、「海洋の10年」についての認識を高める。
IOC/ユネスコが2024年から2025年にかけて選出した15人の専門家は、10数カ国から集まり、政府、民間企業、慈善団体、市民社会、科学界から構成されている。
ディケイド諮問委員会のメンバーを紹介する:

西インド諸島大学環境地理学教授。主な科学的専門分野は、気候変動への適応と小島嶼部における食料システム。気候変動に関する政府間パネル」、「生物多様性と生態系サービスに関する政府間科学・政策プラットフォーム」、「世界海洋評価」、「地球環境展望」など、複数の政府間科学評価に貢献。地域レベルでは現在、カリブ海技術ニーズ評価地域センターの代表を務め、カリブ海の回復力と復興に関する知識ネットワークの共同ディレクターを務める。

アワ・ブッソ・ドラメは、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンの沿岸科学、GIS、AIのセネガル人とカボベルデ人の研究者。CoastGIS Research Institute」のCEOでもある。アワの専門知識は、2023年の「フォーブス・アフリカ30アンダー30sクラス」や2022年の「ロレアル-ユネスコ科学分野の女性賞」を通じて国際的に認められている:西アフリカにおける国境を越えた沿岸・海洋システムのモニタリングのためのAIとGISの結合に関する研究、およびSTEMにおける男女平等の推進が評価された。アワは、さまざまな教育プログラムを通じて研究を社会的インパクトにつなげ、政府や国際機関における政策立案を支援している。アワは現在、西アフリカの16カ国と150人以上の女性と女児を対象としたジェンダーとSTEMの教育プログラムに加え、カボベルデで沿岸研究のイニシアチブを展開している。

リンダ・フォークナーは現在、ニュージーランド・ユネスコ国内委員会の自然科学委員であり、ニュージーランドの「持続可能な海」国家科学チャレンジの副ディレクター、Tūtaiao Ltd.のディレクターでもある。- のディレクターを務める。リンダは、主にニュージーランド・アオテアロアのンガティ・ランギとワンガヌイの部族出身で、先住民の知識と実践を現代科学と並行させることで可能となる機会と利益を長年提唱してきた。ナショナル・サイエンス・チャレンジの分野では、先住民の知識が学際的・複合的な研究に貢献する方法を変革し、そのようなアプローチから得られる大きな利益と影響を目の当たりにしてきた。

ホセ・マリア・フィゲレス・オルセンは、コスタリカ大統領として、環境、経済、社会問題を結びつける包括的な持続可能な開発戦略を主導した。その功績が認められ、GEFによる初のグローバル・リーダーシップ賞を含む数々の国際的な賞を受賞。退任後は、初の国連ICTタスクフォースを率いた。その後、世界経済フォーラムに参加し、初代CEOに就任。その後、カーボン・ワー・ルームの会長として、世界経済において炭素排出量を削減することで利益を得ることができる分野の特定を主導した。また、フィゲレス総裁は、海洋劣化の原因究明と回復に向けた行動を定義するための「世界海洋委員会」の立ち上げに尽力し、同委員会の共同議長を務めた。Pristine Seas、ORRAAの理事を務め、Antarctica 2020の共同設立者でもある。ホセ・マリアはまた、SICPAラテンアメリカのエグゼクティブ・チェアマンであり、Tojoy Shared Holding Groupの共同会長でもある。フィゲレス大統領は、米国陸軍士官学校(ウェストポイント)とハーバード大学ケネディ行政大学院を卒業している。

ギデオン・ヘンダーソン教授は、英国環境・食糧・農村地域省(Defra)の最高科学顧問であり、同省が政策決定に依拠するエビデンスの質を監督する責任を負っている。また、大臣に科学的助言を提供し、科学研究と証拠収集の優先順位を決める。2006年よりオックスフォード大学地球科学科教授。また、オックスフォード大学ユニバーシティ・カレッジの上級研究員、コロンビア大学ラモント・ドハティ地球観測所の非常勤準研究員でもある。2016年第30回プリマス海洋科学メダル、2001年欧州地球科学連合優秀若手科学者賞、2001年レヴァーハルム賞フェローシップなどを受賞。2013年、英国王立協会フェローに選出。
ギデオンはディケイド諮問委員会の2期目を終える。

ミシェル・ホイペル博士はオーストラリアの統合海洋観測システムのディレクター。海洋捕食者(主にサメと魚類)の生態学、保護、管理に25年以上の経験を持つ研究科学者。大学、公的研究機関、民間の非営利研究所、合弁事業など、海洋科学のさまざまな分野でキャリアを積んできた。ミッシェルは200以上の査読付き科学論文を発表し、複数の科学ジャーナルで編集長を務め、科学、保護、管理に関連する国内外の委員会の委員を歴任、または現在も務めている。英連邦絶滅危惧種科学委員会の元メンバーであり、2016年と2018年には移動性種条約サメMOU会議のオーストラリア代表団のメンバーでもあった。

シャーロット・ハドソンは、ピュー・チャリタブル・トラスト(米国ワシントンD.C.)の科学助成プログラムであるレンフェスト・オーシャン・プログラムのプロジェクト・ディレクター。研究テーマを特定し、研究を利用する可能性のある人々との意図的な関わりを含む研究プロジェクトの設計と実施を監督する。また、政策決定に情報を提供し、海洋の持続可能な管理を促進するような形で、研究結果への関与と伝達を監督している。シャーロットは、意思決定における科学、慈善活動、政策の役割について多くの論文を共著している。デビッドソン・カレッジで生物学の学士号を、デューク大学ニコラス環境大学院で環境管理の修士号を取得。
シャーロットは、ディケイド諮問委員会の2期目を終えている。

デンマーク気象研究所国立気候研究センター所長。知識と政策の架け橋として長年の経験を持ち、現在、気候科学と海洋学を国民の意識向上、政策立案、実用化に結びつけている。また、「国連海洋の10年」のデンマーク、グリーンランド、フェローの委員会の委員長も務めている。

セーシェルと英国の弁護士。海洋法と天然資源法を専門とし、環境法の法学修士号を取得。また、国連のAOSIS気候変動フェローシップ・プログラムで研修を受けた気候変動交渉官でもある。カリブ海、太平洋、インド洋のさまざまな国で、持続可能な漁業、国家管轄内外の海洋生物多様性の持続可能な管理、気候変動、特に気候変動への適応と気候変動資金に関する幅広いプロジェクトに携わる。また、国連海洋法委員会第6委員会アフリカ部会の法律専門家も務めた。また、セーシェル国内外の非営利団体の共同設立者や理事として、市民社会と協力した経験もある。
アンジェリークはディケイド諮問委員会の2期目を終える。

ジュリー・ライマー博士海洋社会科学者であり、カナダ漁業海洋省海洋空間計画(MSP)プログラムのシニア・ポリシー・アドバイザー。さまざまな職務において、世界的な保全と持続可能性の目標に向けた道筋としてのMSPの普及を目指している。ジュリーは地理学の博士号、海洋管理の修士号、生物学の理学士号を取得し、MSPの実践と研究において学際的な視点を発揮している。彼女は組織統治、若者のエンパワーメント、科学に基づくアドボカシーのリーダーとして認められている。2021年、ジュリーはカナダの「30歳以下のサステナビリティ・リーダー・トップ30」に選ばれた。

東京大学大気海洋研究所(AORI)教授 ・所長顧問。それ以前は、北海道と東北の国立水産研究所に30年以上勤務。海洋生態系の動態と生物地球化学的循環における生物の役割、およびそれらが自然および人為的擾乱にどのように応答するかを研究している。2018年から2023年まで日本学術会議海洋生物圏統合研究(IMBER)-日本国内委員会の委員長を務め、現在はJournal of Oceanographyの編集長を務める。

H/OEHS Exposure Scenario Tool (IHEST)科学評議会メンバー。フランス、オーストラリア、中国、アフリカの大規模自治体や産業界において、水産業と循環経済に30年の経験を持つ。マルクは、廃水や暴風雨管理、都市清掃サービス、海水淡水化、帯水層涵養、工業団地の集中廃水施設など、さまざまな沿岸地域社会と協力してきた。

ケイティ・ソアピ博士は、太平洋共同体(SPC、ニューカレドニア)の海洋科学太平洋共同体センターのコーディネーターである。それ以前は、フィジーの南太平洋大学(USP)で太平洋天然物研究センターのマネージャーを務める。太平洋島嶼国政府と協力し、アクセスと利益配分に関するガイドラインや政策の策定を支援してきた。ケイティは、海洋遺伝資源に関するアドバイザーとして、国連における国家管轄権の及ばない地域における海洋生物多様性(BBNJ)プロセスで太平洋島嶼国を支援している。ケイティは、キャリアの浅い海洋専門家の能力開発に情熱を注いでおり、コミュニティ・レベルでも活躍している。ケイティはUSPで学士号、オーストラリアのシドニー大学で修士号、英国のイースト・アングリア大学で博士号を取得。ソロモン諸島のレンドバ島育ち。
ケイティはディケイド諮問委員会の2期目を終えている。

アレクサンダー・トゥラ博士は、サンパウロ大学海洋学研究所(IOUSP、ブラジル)の教授であり、海洋学研究所とサンパウロ大学高等研究所を拠点とするユネスコ海洋持続性講座のコーディネーターです。トゥラは、学際的かつ統合的な研究を行う生物学者で、海洋生物多様性、ガバナンス、統合管理、海洋保全、環境影響評価、気候変動、海洋汚染(海洋ごみ)などのテーマに焦点を当てています。トゥラは、科学と社会、政策立案者と民間企業の統合を促進し、公共政策や海洋に適用される技術開発とイノベーションを支援することを目指しています。
アレクサンダーはディケイド諮問委員会の2期目を終える。

ニナ・ワンビジ博士は、ケニア海洋水産研究所(KMFRI)で19年間、上級研究員として勤務。KMFRIでは漁業部門の責任者として副所長を務める。ニナはまた、西インド洋海洋科学協会(WIOMSA)の副会長でもある。同協会は、沿岸・海洋空間の研究と普及、能力開発、知識の共有、科学と政策の連携、研究介入に対する認識の向上を推進している。2014年よりWIOMSAのケニア担当コーディネーター。